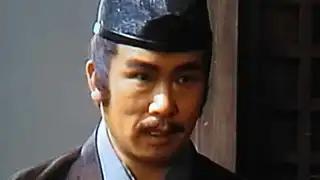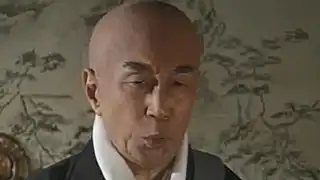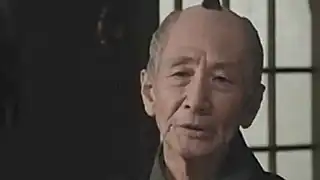 偉人
偉人会沢正志斎
あいざわ せいしさい(1782-1863)
登場回数:1作
会沢 正志斎(あいざわ せいしさい、天明2年5月25日(1782年7月5日) - 文久3年7月14日(1863年8月27日))は、江戸時代後期から末期(幕末)の水戸藩士、水戸学藤田派の学者・思想家。名は安(やすし)。字は伯民。通称は恒蔵。号は正志斎、欣賞斎、憩斎。
登場回数:1作
会沢 正志斎(あいざわ せいしさい、天明2年5月25日(1782年7月5日) - 文久3年7月14日(1863年8月27日))は、江戸時代後期から末期(幕末)の水戸藩士、水戸学藤田派の学者・思想家。名は安(やすし)。字は伯民。通称は恒蔵。号は正志斎、欣賞斎、憩斎。