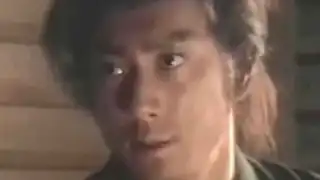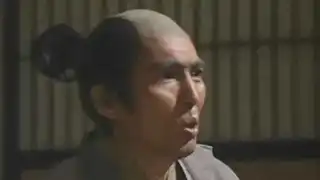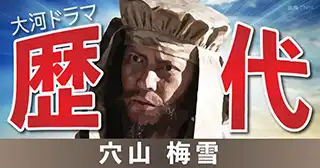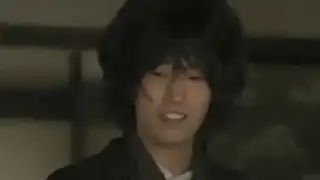偉人
偉人久昌院
きゅうしょういん(1604-1662)
登場回数:1作
別名:谷久子
久昌院(きゅうしょういん、慶長9年(1604年) - 寛文元年11月14日(1662年1月4日))は、常陸水戸藩初代藩主・徳川頼房の側室。水戸藩2代藩主・徳川光圀及び高松松平家の祖・松平頼重の生母。父は谷重則。母は伊藤七郎兵衛の娘。名は久子。
登場回数:1作
別名:谷久子
久昌院(きゅうしょういん、慶長9年(1604年) - 寛文元年11月14日(1662年1月4日))は、常陸水戸藩初代藩主・徳川頼房の側室。水戸藩2代藩主・徳川光圀及び高松松平家の祖・松平頼重の生母。父は谷重則。母は伊藤七郎兵衛の娘。名は久子。