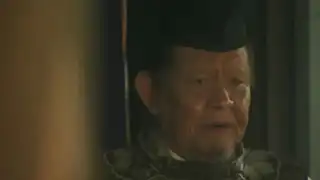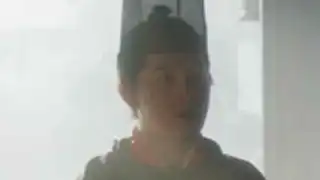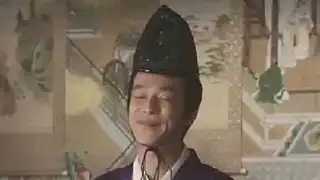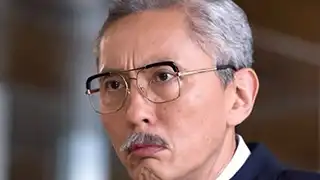 偉人
偉人東龍太郎
あずま りょうたろう(1893-1983)
登場回数:1作
東 龍太郎(あずま りょうたろう、1893年〈明治26年〉1月16日 - 1983年〈昭和58年〉5月26日)は、日本の医学者・官僚。東京大学名誉教授。 東京都知事(第4・5代)、日本赤十字社社長(第10代)等を歴任した。 位階勲等は正三位勲一等旭日桐花大綬章。学位は医学博士(東京帝国大学)。称号は東京都名誉都民、日本赤十字社名誉社長等。 父・藤九郎は医師。弟の東武雄は、東大野球部の投手として活躍。妻は東京帝国大学総長を務めた山川健次郎(枢密顧問官、男爵)の三女・照子。
登場回数:1作
東 龍太郎(あずま りょうたろう、1893年〈明治26年〉1月16日 - 1983年〈昭和58年〉5月26日)は、日本の医学者・官僚。東京大学名誉教授。 東京都知事(第4・5代)、日本赤十字社社長(第10代)等を歴任した。 位階勲等は正三位勲一等旭日桐花大綬章。学位は医学博士(東京帝国大学)。称号は東京都名誉都民、日本赤十字社名誉社長等。 父・藤九郎は医師。弟の東武雄は、東大野球部の投手として活躍。妻は東京帝国大学総長を務めた山川健次郎(枢密顧問官、男爵)の三女・照子。