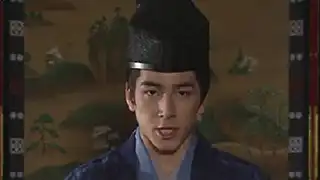偉人
偉人片桐貞隆
かたぎり さだたか(1560-1627)
登場回数:1作
別名:駒千代
片桐 貞隆(かたぎり さだたか)は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。大和国小泉藩の初代藩主。 片桐直貞の次男で、片桐且元の弟である。21歳の時に兄と共に豊臣秀吉に仕え、播磨国に150石の所領を与えられた。その後、小田原征伐、文禄の役などに従軍したことから、播磨国内に1万石余の所領を与えられる。秀吉没後は兄と共にその子豊臣秀頼に仕え、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは西軍に就いて大津城の戦いに加わったが、所領は安堵された。慶長19年(1614年)6月、大野治長と共に徳川家康の口添えで5千石を秀頼より加増され、その礼として治長と駿府にいる大御所家康、次いで江戸の将軍徳川秀忠を訪ねる。しかし、大坂に戻ってくるなり方広寺鐘銘問題が噴出し、これを契機に家康との内通を疑われるようになり、兄と共に豊臣家の下を去って家康に仕えるようになり、大坂夏の陣の後、1615年、大和国小泉に1万6千石を知行された。 兄より遥かに激しい気性の持ち主であったと言われている。
登場回数:1作
別名:駒千代
片桐 貞隆(かたぎり さだたか)は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。大和国小泉藩の初代藩主。 片桐直貞の次男で、片桐且元の弟である。21歳の時に兄と共に豊臣秀吉に仕え、播磨国に150石の所領を与えられた。その後、小田原征伐、文禄の役などに従軍したことから、播磨国内に1万石余の所領を与えられる。秀吉没後は兄と共にその子豊臣秀頼に仕え、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは西軍に就いて大津城の戦いに加わったが、所領は安堵された。慶長19年(1614年)6月、大野治長と共に徳川家康の口添えで5千石を秀頼より加増され、その礼として治長と駿府にいる大御所家康、次いで江戸の将軍徳川秀忠を訪ねる。しかし、大坂に戻ってくるなり方広寺鐘銘問題が噴出し、これを契機に家康との内通を疑われるようになり、兄と共に豊臣家の下を去って家康に仕えるようになり、大坂夏の陣の後、1615年、大和国小泉に1万6千石を知行された。 兄より遥かに激しい気性の持ち主であったと言われている。