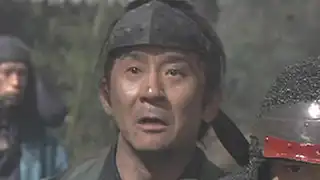 偉人
偉人井上源三郎
いのうえ げんざぶろう(1829-1868)
登場回数:1作
井上 源三郎(いのうえ げんざぶろう、文政12年3月1日(1829年4月4日) - 慶応4年1月5日(1868年1月29日))は、新選組の六番隊組長。諱は一重、後に一武(かずたけ)。
登場回数:1作
井上 源三郎(いのうえ げんざぶろう、文政12年3月1日(1829年4月4日) - 慶応4年1月5日(1868年1月29日))は、新選組の六番隊組長。諱は一重、後に一武(かずたけ)。
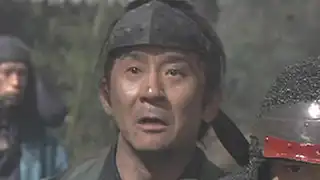 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人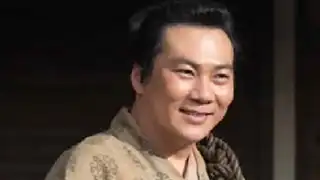 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人