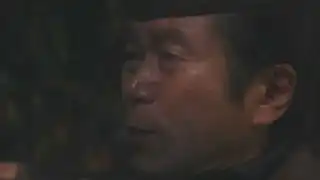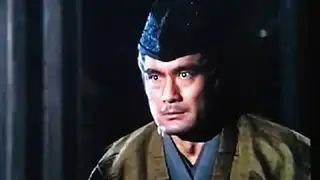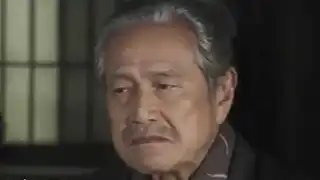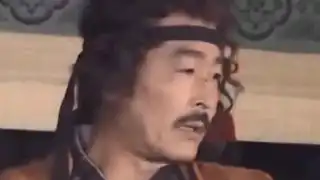偉人
偉人荒木政羽
あらき まさはね(1662-1732)
登場回数:4作
別名:荒木十左衛門
荒木 政羽(あらき まさはね / あらき まさは、寛文2年(1662年) - 享保17年2月14日(1732年3月10日))は、江戸時代前期の武士。江戸幕府の旗本。通称は與十郎・内蔵助・十左衛門。官位は従五位下・志摩守。
登場回数:4作
別名:荒木十左衛門
荒木 政羽(あらき まさはね / あらき まさは、寛文2年(1662年) - 享保17年2月14日(1732年3月10日))は、江戸時代前期の武士。江戸幕府の旗本。通称は與十郎・内蔵助・十左衛門。官位は従五位下・志摩守。