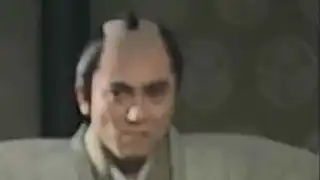偉人
偉人小松原英太郎
こまつばら えいたろう(1852-1919)
登場回数:1作
小松原 英太郎(こまつばら えいたろう、嘉永5年2月16日(1852年3月6日) - 大正8年(1919年)12月26日)は、戦前の官僚・政治家。錦鶏間祗候、枢密顧問官、埼玉県知事、静岡県知事、長崎県知事、司法次官、内務次官、文部大臣、農商務大臣、貴族院勅選議員、東洋協会会長、皇典講究所長、大阪毎日新聞社社長、日華学会長、斯文会会長、國學院大學学長、内務省警保局長等、ベルリン公使館駐在を歴任。 拓殖大学第2代学長。 位階勲等は従二位勲一等。
登場回数:1作
小松原 英太郎(こまつばら えいたろう、嘉永5年2月16日(1852年3月6日) - 大正8年(1919年)12月26日)は、戦前の官僚・政治家。錦鶏間祗候、枢密顧問官、埼玉県知事、静岡県知事、長崎県知事、司法次官、内務次官、文部大臣、農商務大臣、貴族院勅選議員、東洋協会会長、皇典講究所長、大阪毎日新聞社社長、日華学会長、斯文会会長、國學院大學学長、内務省警保局長等、ベルリン公使館駐在を歴任。 拓殖大学第2代学長。 位階勲等は従二位勲一等。