 偉人
偉人有吉熊次郎
ありよし くまじろう(1842-1864)
登場回数:1作
有吉 熊次郎(ありよし くまじろう)は、幕末の長州藩士、尊皇攘夷派の志士。熊次郎は通称で、諱は良明、もしくは良朋。本姓は藤原を称し、墓碑の刻字には藤原良明とある。作家有吉佐和子の曾祖父にあたる。
登場回数:1作
有吉 熊次郎(ありよし くまじろう)は、幕末の長州藩士、尊皇攘夷派の志士。熊次郎は通称で、諱は良明、もしくは良朋。本姓は藤原を称し、墓碑の刻字には藤原良明とある。作家有吉佐和子の曾祖父にあたる。
 偉人
偉人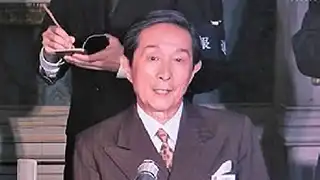 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人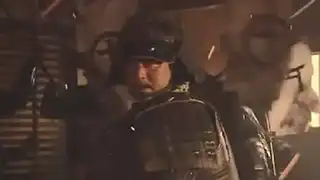 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人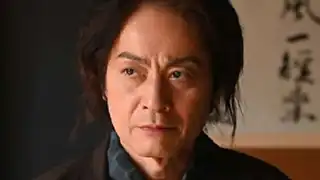 偉人
偉人 偉人
偉人