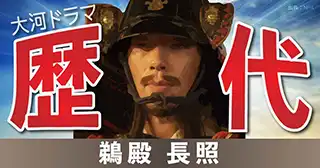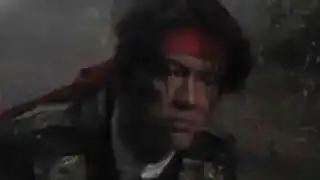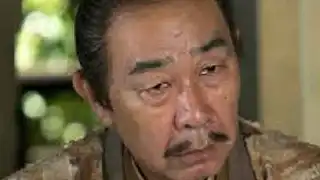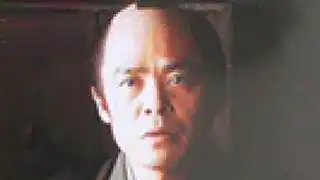 偉人
偉人伊藤軍兵衛
いとう ぐんべえ(1840-1862)
登場回数:1作
伊藤 軍兵衛(いとう ぐんべえ、天保11年(1840年)11月 - 文久2年6月1日(1862年6月27日))は、第二次東禅寺事件を引き起こした攘夷派の志士。信濃国松本藩士。諱は祐英(すけひで)。 松本藩士・伊藤祐宣の子として生まれ、文久元年(1861年)5月、藩主松平光則の参勤交代警護として出仕する。文久2年(1862年)5月28日、イギリス公使館が置かれた東禅寺の警衛役が自藩に割り当てられると、伊藤は父の喪により帰省中であったが、急遽上京して、警護隊に編入された。伊藤は兼ねてから、東禅寺の警衛役により自藩が多くの出費を強いられていること、外国人のために日本人同士が殺しあうことを憂い、公使を殺害し、自藩の東禅寺警衛の任を解くのが上策と考えるに至った。 5月29日午前2時頃、伊藤は一刀を帯し、槍を提げて江戸城近傍の呉服橋の藩邸を抜け出し、東禅寺に忍び込み、イギリス人水兵2名を殺害。早朝藩邸に戻り、遺書を残して翌5月30日に自害した。享年23。 伊藤の遺体は幕府の外国掛によって東禅寺に移され、外国人の一閲に供された後、北町奉行石谷穆清の元に差し出され、小塚原刑場に遺棄されたが、儒者大橋訥庵によって南千住回向院常行庵に埋葬された。 娘・鑚の婿に和算家で大蔵省会計検査院部長を務めた伊藤祐敬。祐敬は松本藩算学師範・中島這季の子で、兄に中島這棄、市川正寧(大蔵省一等主税官)、妹は男爵安東貞美の妻。娘夫婦の長男・伊藤常夫は東京帝国大学工科大学土木工学科を卒業後鉄道省に入省し、退官後富土山麓鉄道の專務取締役。常夫の妻は杉山四五郎の養妹。常夫の妹たちは、天文学者の平山信、男爵木越安綱の長男・専八(軍人)、子爵加納久朗、長崎省吾の長男・守一(軍人)の妻となった。
登場回数:1作
伊藤 軍兵衛(いとう ぐんべえ、天保11年(1840年)11月 - 文久2年6月1日(1862年6月27日))は、第二次東禅寺事件を引き起こした攘夷派の志士。信濃国松本藩士。諱は祐英(すけひで)。 松本藩士・伊藤祐宣の子として生まれ、文久元年(1861年)5月、藩主松平光則の参勤交代警護として出仕する。文久2年(1862年)5月28日、イギリス公使館が置かれた東禅寺の警衛役が自藩に割り当てられると、伊藤は父の喪により帰省中であったが、急遽上京して、警護隊に編入された。伊藤は兼ねてから、東禅寺の警衛役により自藩が多くの出費を強いられていること、外国人のために日本人同士が殺しあうことを憂い、公使を殺害し、自藩の東禅寺警衛の任を解くのが上策と考えるに至った。 5月29日午前2時頃、伊藤は一刀を帯し、槍を提げて江戸城近傍の呉服橋の藩邸を抜け出し、東禅寺に忍び込み、イギリス人水兵2名を殺害。早朝藩邸に戻り、遺書を残して翌5月30日に自害した。享年23。 伊藤の遺体は幕府の外国掛によって東禅寺に移され、外国人の一閲に供された後、北町奉行石谷穆清の元に差し出され、小塚原刑場に遺棄されたが、儒者大橋訥庵によって南千住回向院常行庵に埋葬された。 娘・鑚の婿に和算家で大蔵省会計検査院部長を務めた伊藤祐敬。祐敬は松本藩算学師範・中島這季の子で、兄に中島這棄、市川正寧(大蔵省一等主税官)、妹は男爵安東貞美の妻。娘夫婦の長男・伊藤常夫は東京帝国大学工科大学土木工学科を卒業後鉄道省に入省し、退官後富土山麓鉄道の專務取締役。常夫の妻は杉山四五郎の養妹。常夫の妹たちは、天文学者の平山信、男爵木越安綱の長男・専八(軍人)、子爵加納久朗、長崎省吾の長男・守一(軍人)の妻となった。