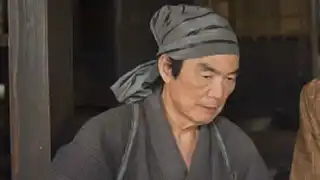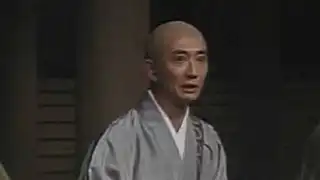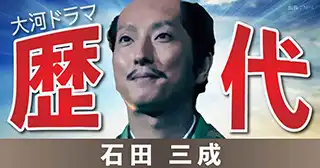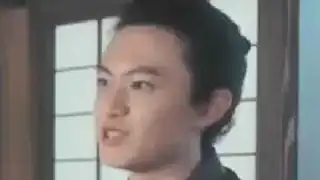偉人
偉人水野忠勝
みずの ただかつ(?-1568)
登場回数:1作
水野 忠勝(みずの ただかつ)は、戦国時代の武将。尾張国知多郡の豪族・水野氏の一族。水野信元・忠重・於大の方は異母兄弟にあたる。 東海道一帯に勢力を持つ戦国大名今川氏に属し、今川義元・氏真の2代に従った。永禄10年(1567年)今川氏と敵対する武田信玄に内通して密書を送ったことが露見したため、自害した。 子の康忠は徳川家康に仕えて樽氏と改姓し、子孫は樽屋と号して代々江戸の町年寄を務めた。また通常水野成清の子とされる水野長勝を、康忠の弟とする系譜もあるという。
登場回数:1作
水野 忠勝(みずの ただかつ)は、戦国時代の武将。尾張国知多郡の豪族・水野氏の一族。水野信元・忠重・於大の方は異母兄弟にあたる。 東海道一帯に勢力を持つ戦国大名今川氏に属し、今川義元・氏真の2代に従った。永禄10年(1567年)今川氏と敵対する武田信玄に内通して密書を送ったことが露見したため、自害した。 子の康忠は徳川家康に仕えて樽氏と改姓し、子孫は樽屋と号して代々江戸の町年寄を務めた。また通常水野成清の子とされる水野長勝を、康忠の弟とする系譜もあるという。