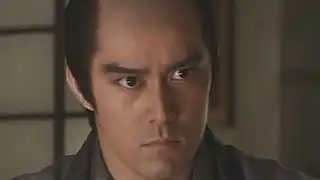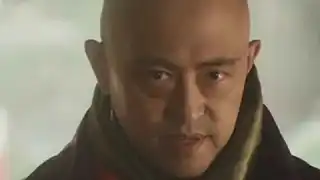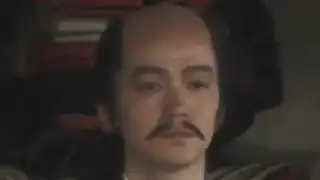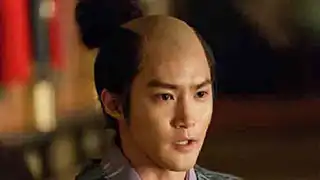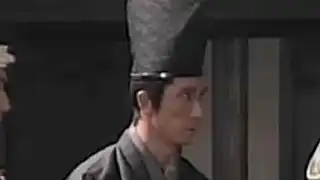 偉人
偉人北条仲時
ほうじょう なかとき(1306-1333)
登場回数:1作
北条 仲時(ほうじょう なかとき)は、鎌倉時代末期の北条氏一門。鎌倉幕府最後の六波羅探題北方であり摂津守護も兼務した。普恩寺流で第13代執権である北条基時の子。普恩寺 仲時(ふおんじ なかとき)とも呼ばれる。
登場回数:1作
北条 仲時(ほうじょう なかとき)は、鎌倉時代末期の北条氏一門。鎌倉幕府最後の六波羅探題北方であり摂津守護も兼務した。普恩寺流で第13代執権である北条基時の子。普恩寺 仲時(ふおんじ なかとき)とも呼ばれる。