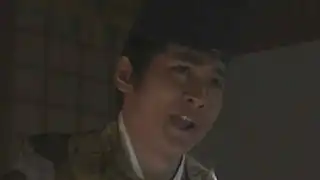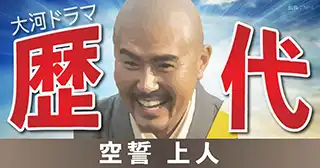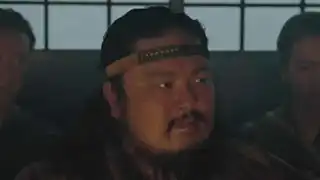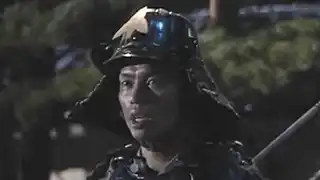紫式部
むらさきしきぶ(?-?)
登場回数:1作
紫式部(むらさきしきぶ)は、平安時代中期の作家・歌人、女房(女官)。作家としては、日本文学史を代表する一人。正確な誕生年は特定できないが、近年の研究では、天禄元年(970年)から天元元年(978年)の間に生まれ、寛仁3年(1019年)までは存命したとされる。 『源氏物語』の作者とされ、藤原道長の要請で宮中に上がった際に宮中の様子を書いた『紫式部日記』も残している。『源氏物語』と『紫式部日記』の2作品は、後にそれぞれ『源氏物語絵巻』『紫式部日記絵巻』として絵画化された。また、歌人としても優れ、子供時代から晩年に至るまで自らが詠んだ和歌から選び収めた家集『紫式部集』がある。『小倉百人一首』にも和歌が収められており、中古三十六歌仙および女房三十六歌仙の一人でもある。『拾遺和歌集』以下の勅撰和歌集に、計51首が入集している。 父の藤原為時は、官位は正五位下と下級貴族ながら、花山天皇に漢学を教えた漢詩人、歌人である。紫式部は藤原宣孝に嫁ぎ、一女(大弐三位)を産んだ。長保3年(1001年)に結婚後3年程で夫が卒去する。その後『源氏物語』を書き始め、その評判を聞いた藤原道長に召し出されて、道長の娘で、一条天皇中宮の彰子に仕えている間に『源氏物語』を完成させた。 なお、『紫式部集』には、夫である藤原宣孝の卒去に伴い詠んだ和歌「見し人の けぶりとなりし 夕べより 名ぞむつましき 塩釜の浦」が収められている。
 偉人
偉人