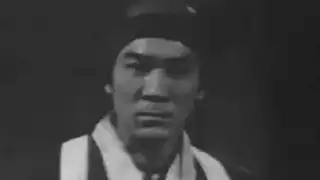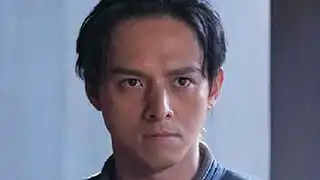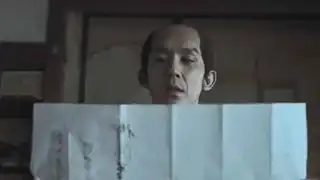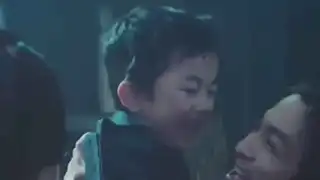偉人
偉人亮賢
りょうけん(1611-1687)
登場回数:1作
亮賢(りょうけん、慶長16年(1611年) - 貞享4年3月7日(1687年4月18日))は、江戸時代前期の新義真言宗の僧。上野国の出身。 故郷・上野国の得成寺で出家し、大和国・長谷寺で密教を修学した。その後自らが出家した得成寺や高崎大聖護国寺の住職となった。卜筮(ぼくぜい)の名声が高く、後に3代将軍徳川家光の側室となるお玉の方(後の桂昌院)を占って、5代将軍・綱吉を産むことを予言したという俗説がある。1681年(天和元年)、綱吉から桂昌院の祈願寺である護国寺の開山を命じられた。
登場回数:1作
亮賢(りょうけん、慶長16年(1611年) - 貞享4年3月7日(1687年4月18日))は、江戸時代前期の新義真言宗の僧。上野国の出身。 故郷・上野国の得成寺で出家し、大和国・長谷寺で密教を修学した。その後自らが出家した得成寺や高崎大聖護国寺の住職となった。卜筮(ぼくぜい)の名声が高く、後に3代将軍徳川家光の側室となるお玉の方(後の桂昌院)を占って、5代将軍・綱吉を産むことを予言したという俗説がある。1681年(天和元年)、綱吉から桂昌院の祈願寺である護国寺の開山を命じられた。