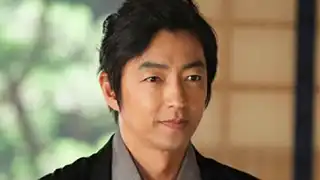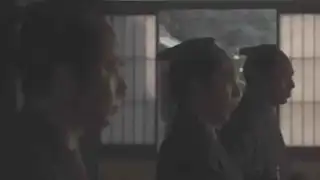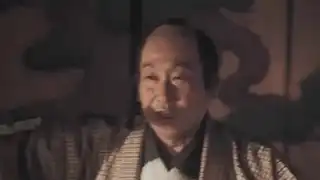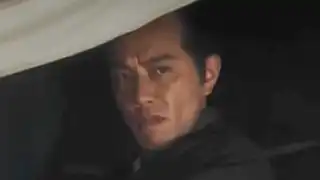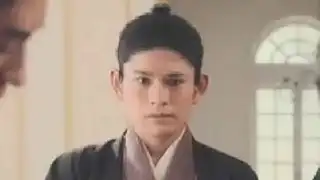偉人
偉人林鳳岡
はやし ほうこう(1645-1732)
登場回数:4作
別名:林大学
林 鳳岡(はやし ほうこう、寛永21年12月14日(1645年1月11日) - 享保17年6月1日(1732年7月22日))は、江戸時代前期・中期の儒学者。特に元禄時代の将軍・徳川綱吉のもと江戸幕府の文治政治の推進に功績があったひとり。父は林鵞峰。名は又四郎・春常・信篤。字は直民。号は鳳岡・整宇。
登場回数:4作
別名:林大学
林 鳳岡(はやし ほうこう、寛永21年12月14日(1645年1月11日) - 享保17年6月1日(1732年7月22日))は、江戸時代前期・中期の儒学者。特に元禄時代の将軍・徳川綱吉のもと江戸幕府の文治政治の推進に功績があったひとり。父は林鵞峰。名は又四郎・春常・信篤。字は直民。号は鳳岡・整宇。