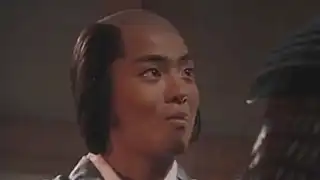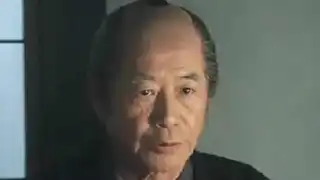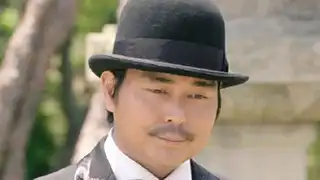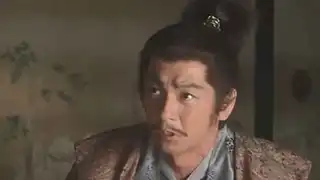 偉人
偉人妻鹿田新助
めかだ しんすけ(?-1552)
登場回数:1作
妻鹿田 新助(めかだ しんすけ、生年不詳 - 天文21年(1552年))は、戦国時代の武将、関東管領山内上杉憲政の家臣。姓は妻方、目方、目加田、目賀田など諸説ある。名は新介とも。親族にあたる九里氏の系譜を見る限り、出自は近江国六角氏家臣の目賀田氏とされる。妻は上杉憲政の嫡子龍若丸の乳母。
登場回数:1作
妻鹿田 新助(めかだ しんすけ、生年不詳 - 天文21年(1552年))は、戦国時代の武将、関東管領山内上杉憲政の家臣。姓は妻方、目方、目加田、目賀田など諸説ある。名は新介とも。親族にあたる九里氏の系譜を見る限り、出自は近江国六角氏家臣の目賀田氏とされる。妻は上杉憲政の嫡子龍若丸の乳母。