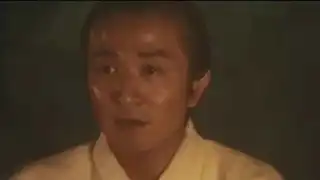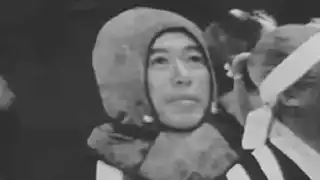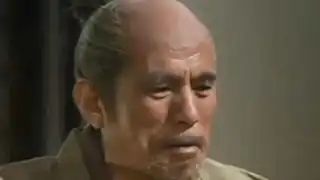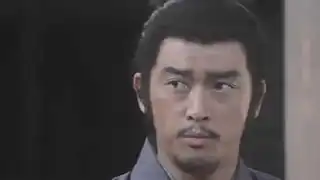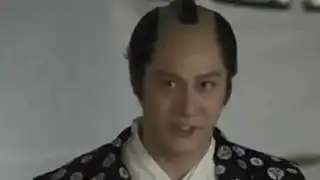偉人
偉人小栗忠順
おぐり ただまさ(1827-1868)
登場回数:5作
小栗 忠順(おぐり ただまさ、文政10年6月23日〈1827年7月16日〉 - 慶応4年閏4月6日〈1868年5月27日〉)は、幕末期の日本の武士(幕臣)。 通称は又一で、この通称は小栗家当主が代々名乗った。安政6年(1859年)、従五位下・豊後守に叙任。文久3年(1863年)、上野介に遷任した。三河小栗氏第12代当主。 勘定奉行、江戸町奉行、外国奉行を歴任した。
登場回数:5作
小栗 忠順(おぐり ただまさ、文政10年6月23日〈1827年7月16日〉 - 慶応4年閏4月6日〈1868年5月27日〉)は、幕末期の日本の武士(幕臣)。 通称は又一で、この通称は小栗家当主が代々名乗った。安政6年(1859年)、従五位下・豊後守に叙任。文久3年(1863年)、上野介に遷任した。三河小栗氏第12代当主。 勘定奉行、江戸町奉行、外国奉行を歴任した。