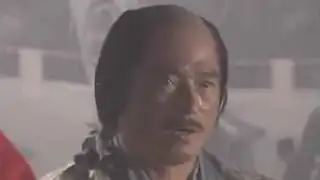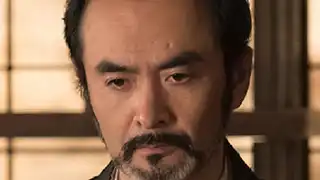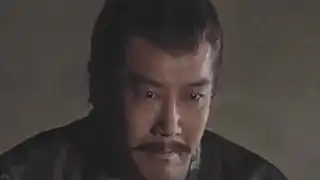偉人
偉人秋元喬知
あきもと たかとも(1649-1714)
登場回数:3作
秋元 喬知(あきもと たかとも)は、江戸時代前期から中期の大名。甲斐谷村藩主、武蔵川越藩主。老中を元禄12年(1699年)から正徳4年(1714年)まで務めた。館林藩秋元家4代。実父の戸田忠昌、実弟の戸田忠真と共に老中を務めた。
登場回数:3作
秋元 喬知(あきもと たかとも)は、江戸時代前期から中期の大名。甲斐谷村藩主、武蔵川越藩主。老中を元禄12年(1699年)から正徳4年(1714年)まで務めた。館林藩秋元家4代。実父の戸田忠昌、実弟の戸田忠真と共に老中を務めた。