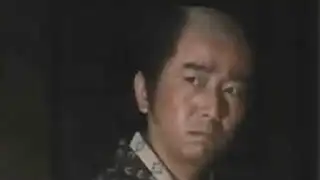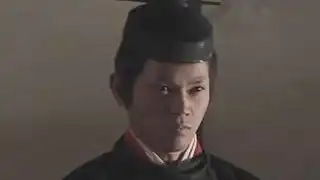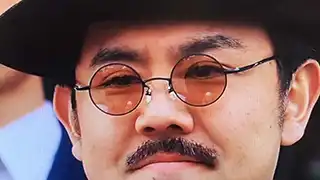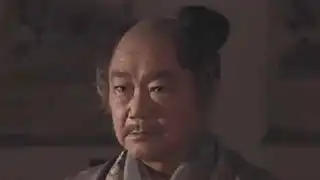 偉人
偉人大久保忠隣
おおくぼ ただちか(1553-1628)
登場回数:5作
大久保 忠隣(おおくぼ ただちか)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・譜代大名。相模小田原藩の初代藩主。父は大久保忠世、母は近藤幸正の娘。講談で有名な旗本の大久保忠教の甥にあたる。小田原藩大久保家初代。
登場回数:5作
大久保 忠隣(おおくぼ ただちか)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・譜代大名。相模小田原藩の初代藩主。父は大久保忠世、母は近藤幸正の娘。講談で有名な旗本の大久保忠教の甥にあたる。小田原藩大久保家初代。