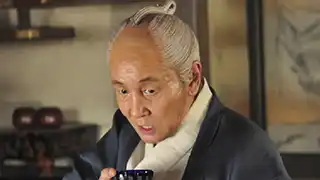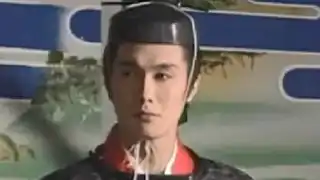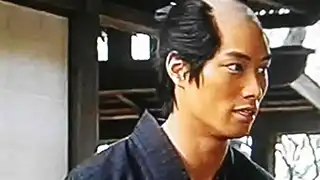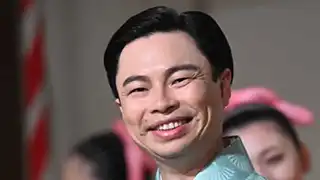 偉人
偉人三波春夫
みなみ はるお(1923-2001)
登場回数:1作
三波 春夫(みなみ はるお、1923年7月19日 - 2001年4月14日、本名:北詰 文司(きたづめ ぶんじ))は、新潟県三島郡越路町(現・長岡市)出身の浪曲師、演歌歌手。紫綬褒章受章、勲四等旭日小綬章受章、新潟県民栄誉賞受賞。自身の長編歌謡浪曲などの作詞・構成時のペンネームとして「北村 桃児(きたむら とうじ)」を用いた。俳号は「北桃子(ほくとうし)」。
登場回数:1作
三波 春夫(みなみ はるお、1923年7月19日 - 2001年4月14日、本名:北詰 文司(きたづめ ぶんじ))は、新潟県三島郡越路町(現・長岡市)出身の浪曲師、演歌歌手。紫綬褒章受章、勲四等旭日小綬章受章、新潟県民栄誉賞受賞。自身の長編歌謡浪曲などの作詞・構成時のペンネームとして「北村 桃児(きたむら とうじ)」を用いた。俳号は「北桃子(ほくとうし)」。