船津伝次平
ふなつ でんじべい(1832-1898)
登場回数:1作
船津伝次平(ふなつ でんじべい、天保3年11月1日(1832年11月22日) - 明治31年(1898年)6月15日)は、幕末から明治時代にかけて活動した農業研究家。 幼名は船津市造。上野国原之郷(後の群馬県勢多郡富士見村大字原之郷、現・群馬県前橋市富士見町原之郷)出身。篤農家として評価された「明治の三老農」の一人であり、元駒場農学校及び東京帝国大学講師。 幕末、出身地の名主・村役人として名望を集める傍ら、実践的な農業技術の改良にあたり、成功を収める。その実績を買われて明治維新後は中央に招かれ、引き続き農業技術の改良に取り組みながら、講演等で生涯にわたって各地の農業振興に努めた。日本の在来農法を基礎に改良しながら、西洋農法の手法をも部分的に折衷した「船津農法」の考案者である。46歳の時に群馬県赤城山麓の農業指導者から駒場農学校の教官に抜てきされ、講義の傍ら、自ら先頭に立って学生達と一緒に駒場の原野に開墾のクワをふるって農場を拓き、実習田をつくった。経験を重んじる在来の日本農業に西洋の近代農法を積極的に採り入れた「混同農事」に力を入れ、その後、この農法は全国に普及していった。
 偉人
偉人 偉人
偉人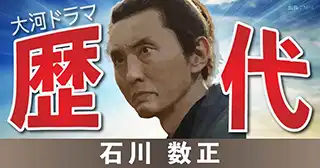 偉人
偉人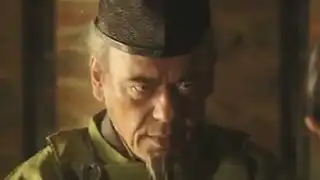 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人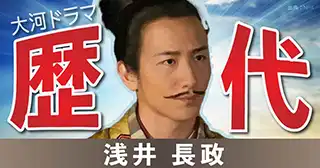 偉人
偉人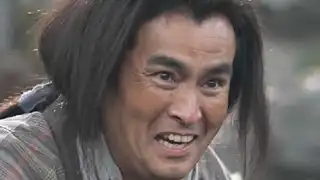 偉人
偉人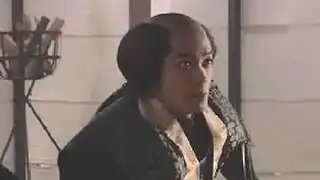 偉人
偉人 偉人
偉人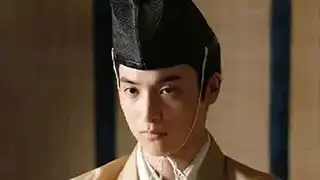 偉人
偉人