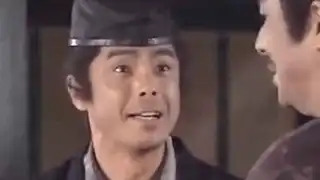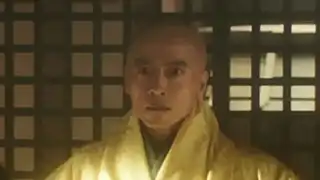偉人
偉人辰路
たつじ(1846-1910)
登場回数:1作
辰路(たつじ、弘化3年(1846年) - 明治43年(1910年))は、京都島原桔梗屋の芸妓である。本名、井筒タツ。辰次、お辰とも。 久坂玄瑞となじみ深く、その息子・秀次郎は辰路との間の子であるとも、伏見にいたもう一人の馴染みの女性との子であるともいわれる。 明治3年(1870年)4月、当時の角屋当主(十代目)と桔梗屋の女将の仲立ちによって、下京の裕福な農家の竹岡甚之助と結婚する。 明治43年(1910年)、他界。65歳であった。 墓所は京都市西七条の「安阿弥寺」にある。
登場回数:1作
辰路(たつじ、弘化3年(1846年) - 明治43年(1910年))は、京都島原桔梗屋の芸妓である。本名、井筒タツ。辰次、お辰とも。 久坂玄瑞となじみ深く、その息子・秀次郎は辰路との間の子であるとも、伏見にいたもう一人の馴染みの女性との子であるともいわれる。 明治3年(1870年)4月、当時の角屋当主(十代目)と桔梗屋の女将の仲立ちによって、下京の裕福な農家の竹岡甚之助と結婚する。 明治43年(1910年)、他界。65歳であった。 墓所は京都市西七条の「安阿弥寺」にある。