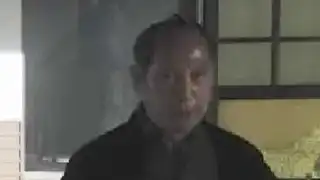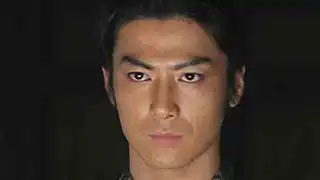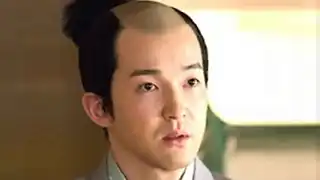 偉人
偉人小早川秀秋
こばやかわ ひであき(1582-1602)
登場回数:9作
別名:木下辰之助/木下秀俊/羽柴秀俊/小早川秀詮
小早川 秀秋(こばやかわ ひであき)は、安土桃山時代の大名。丹波国亀山城主、筑前国名島城主を経て備前国岡山城主。名は関ヶ原の戦いの後に秀詮(ひであき)と改名した。 豊臣秀吉の正室・高台院の甥。秀吉の親族として豊臣家では重きをなし、小早川隆景と養子縁組した後には、関ヶ原の戦いで徳川家康の東軍に寝返り、豊臣家衰退の契機を作った。
登場回数:9作
別名:木下辰之助/木下秀俊/羽柴秀俊/小早川秀詮
小早川 秀秋(こばやかわ ひであき)は、安土桃山時代の大名。丹波国亀山城主、筑前国名島城主を経て備前国岡山城主。名は関ヶ原の戦いの後に秀詮(ひであき)と改名した。 豊臣秀吉の正室・高台院の甥。秀吉の親族として豊臣家では重きをなし、小早川隆景と養子縁組した後には、関ヶ原の戦いで徳川家康の東軍に寝返り、豊臣家衰退の契機を作った。