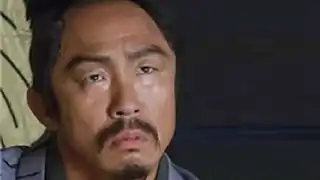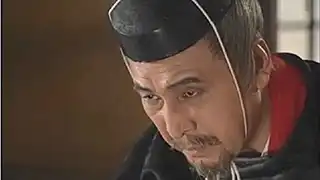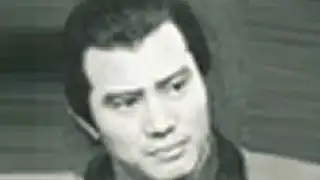偉人
偉人大石弥太郎
おおいし やたろう(1829-1916)
登場回数:1作
大石 弥太郎(おおいし やたろう、1829年11月30日(文政12年10月17日) - 1916年(大正5年)10月30日)は、日本の土佐藩士、迅衝隊士。弥太郎は通称で、諱は初め元敬、のち圓(まどか)と改めた。位階は従五位。 土佐勤王党結成に尽力し、盟約書の起草を手掛けるなど同党幹部として活動、戊辰戦争においては板垣退助の率いる迅衝隊で小軍監などを務め各地を転戦した。明治維新後は新政府に出仕するが程なく辞し、以降は高知政界における「古勤王党派」の中心人物として影響力を有した。 同じく勤王党員で吉田東洋暗殺の実行犯の大石団蔵は従兄弟にあたる。
登場回数:1作
大石 弥太郎(おおいし やたろう、1829年11月30日(文政12年10月17日) - 1916年(大正5年)10月30日)は、日本の土佐藩士、迅衝隊士。弥太郎は通称で、諱は初め元敬、のち圓(まどか)と改めた。位階は従五位。 土佐勤王党結成に尽力し、盟約書の起草を手掛けるなど同党幹部として活動、戊辰戦争においては板垣退助の率いる迅衝隊で小軍監などを務め各地を転戦した。明治維新後は新政府に出仕するが程なく辞し、以降は高知政界における「古勤王党派」の中心人物として影響力を有した。 同じく勤王党員で吉田東洋暗殺の実行犯の大石団蔵は従兄弟にあたる。