 偉人
偉人伊達政宗
だて まさむね(1567-1636)
登場回数:12作
別名:梵天丸
伊達 政宗(だて/いだて まさむね)は、出羽国(山形県)と陸奥国(宮城県、福島県)の武将・戦国大名。伊達氏の第17代当主。近世大名としては、仙台藩(宮城県、岩手県南部)の初代藩主である。
登場回数:12作
別名:梵天丸
伊達 政宗(だて/いだて まさむね)は、出羽国(山形県)と陸奥国(宮城県、福島県)の武将・戦国大名。伊達氏の第17代当主。近世大名としては、仙台藩(宮城県、岩手県南部)の初代藩主である。
 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人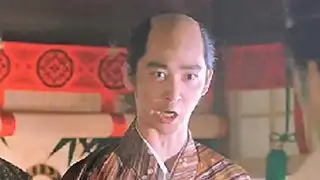 偉人
偉人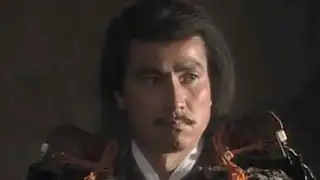 偉人
偉人 偉人
偉人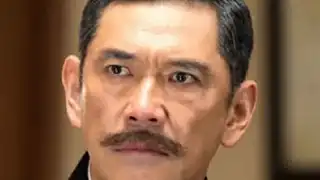 偉人
偉人 偉人
偉人