上杉景勝
うえすぎ かげかつ(1556-1623)
登場回数:7作
別名:上杉顕景
上杉 景勝(うえすぎ かげかつ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけての大名。豊臣政権の五大老の一人。米沢藩の初代藩主。山内上杉家17代目。 上田長尾家出身で、初名は長尾顕景。同じ長尾家出身の叔父・上杉謙信の養子となり、名を上杉景勝と改めた。実子のいない謙信の死後、上杉家の家督相続を争った御館の乱で勝利し、謙信の後継者として上杉家の当主となった。 豊臣秀吉に仕え、豊臣家五大老の1人として、会津藩120万石(「上杉家記」では120万1200石余、上方の在京領は除く)を領した。秀吉の死後、徳川家康が景勝討伐に向かい関ヶ原の戦いが幕開け、景勝は石田三成ら西軍に付き敗北した。戦後に、徳川家康から上杉家の存続は許されたが米沢藩30万石へ減封となった。
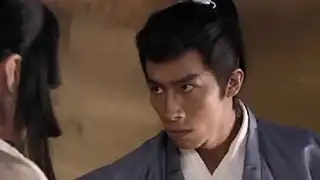 偉人
偉人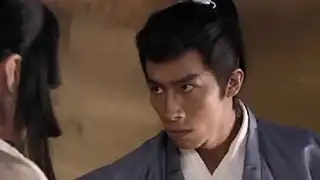 偉人
偉人 偉人
偉人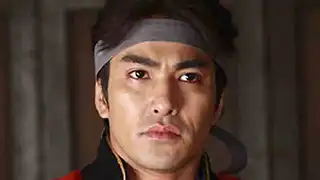 偉人
偉人 偉人
偉人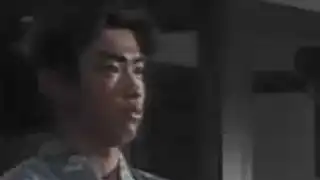 偉人
偉人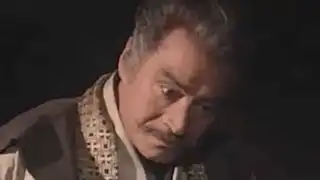 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人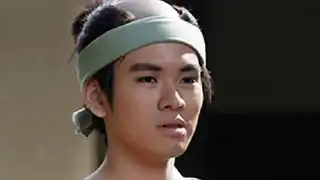 偉人
偉人 偉人
偉人