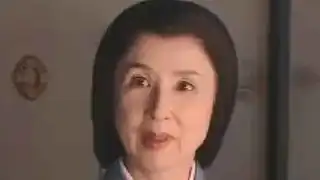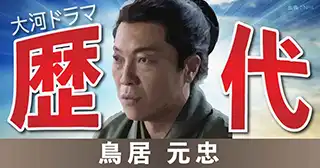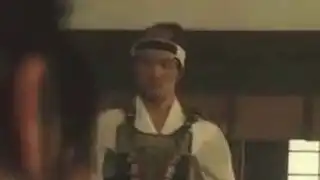 偉人
偉人竹中重矩
たけなか しげのり(1546-1582)
登場回数:2作
竹中 重矩(たけなか しげのり、天文15年(1546年) - 天正10年6月6日(1582年6月25日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。美濃斎藤氏、織田氏の家臣。竹中重元の子。通称は彦作、久作。妻は中川重政の姉妹。
登場回数:2作
竹中 重矩(たけなか しげのり、天文15年(1546年) - 天正10年6月6日(1582年6月25日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。美濃斎藤氏、織田氏の家臣。竹中重元の子。通称は彦作、久作。妻は中川重政の姉妹。