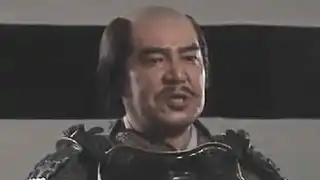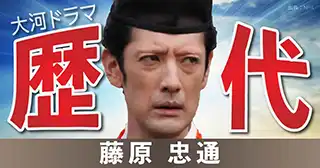 偉人
偉人藤原忠通
ふじわら の ただみち(1097-1164)
登場回数:2作
藤原 忠通(ふじわら の ただみち)は、平安時代後期から末期にかけての公卿・歌人。藤原北家、関白・藤原忠実の次男。官位は従一位・摂政 関白・太政大臣。通称は法性寺関白(ほっしょうじ かんぱく)。小倉百人一首では法性寺入道前関白太政大臣。
登場回数:2作
藤原 忠通(ふじわら の ただみち)は、平安時代後期から末期にかけての公卿・歌人。藤原北家、関白・藤原忠実の次男。官位は従一位・摂政 関白・太政大臣。通称は法性寺関白(ほっしょうじ かんぱく)。小倉百人一首では法性寺入道前関白太政大臣。