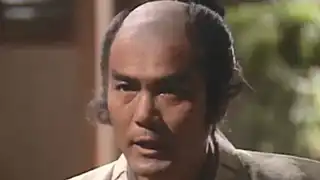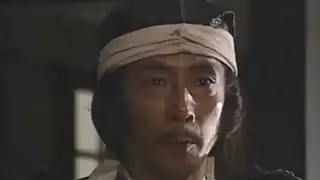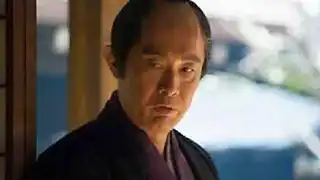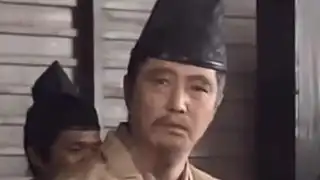 偉人
偉人北条時広
ほうじょう ときひろ(1222-1275)
登場回数:1作
北条 時広(ほうじょう ときひろ)は鎌倉時代中期の北条氏の一門。父は北条時房の次男・北条時村。 父時村は承久2年(1220年)に弟(時広の叔父)の資時と共に出家し、嘉禄元年(1225年)12月に没した。時広は祖父時房の養子となり、引付衆、評定衆、四番引付頭人の要職を務めた。建治元年(1275年)6月25日、54歳で没。 男子はなく、時村流は時広の甥で兄時隆の子宗房が継いでいる。 和歌が得意で将軍の歌席寄人や歌仙結番に選ばれている。北条家一門随一の風流文化人でもあった。
登場回数:1作
北条 時広(ほうじょう ときひろ)は鎌倉時代中期の北条氏の一門。父は北条時房の次男・北条時村。 父時村は承久2年(1220年)に弟(時広の叔父)の資時と共に出家し、嘉禄元年(1225年)12月に没した。時広は祖父時房の養子となり、引付衆、評定衆、四番引付頭人の要職を務めた。建治元年(1275年)6月25日、54歳で没。 男子はなく、時村流は時広の甥で兄時隆の子宗房が継いでいる。 和歌が得意で将軍の歌席寄人や歌仙結番に選ばれている。北条家一門随一の風流文化人でもあった。