賢俊
けんしゅん(1299-1357)
登場回数:1作
賢俊(けんしゅん)は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての真言宗の僧・歌人。第65代醍醐寺座主・東寺長者・大僧正。父は権大納言日野俊光。兄に日野資名・資朝。室町幕府初代将軍足利尊氏の腹心の一人。 建武の乱(1336年)で持明院統(後の北朝)の光厳上皇の院宣を足利尊氏に伝えるなど、幕府・北朝成立に主たる功績を果たした。室町幕府の初代武家護持僧(祈祷の霊力で征夷大将軍を守護する僧)を務め、並ぶ者のない権勢を得た。南朝護持僧の文観房弘真とは、真言宗の盟主の地位を激しく争ったとするのが伝統的通説だが、同時代史料を見る限り実際は文観とは緩やかな協調関係にあったとする説もある。 著作のうち『紙本墨書賢俊日記』・『紙本墨書弘法大師二十五箇條遺告賢俊筆』の2件が重要文化財に指定されている。歌人としては『風雅和歌集』以下の勅撰和歌集に10首が入集。
 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人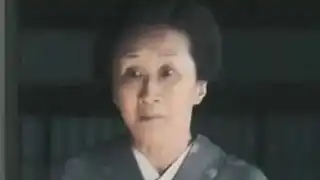 偉人
偉人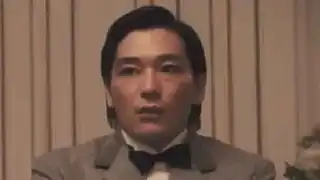 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人