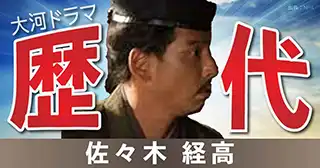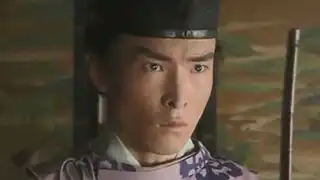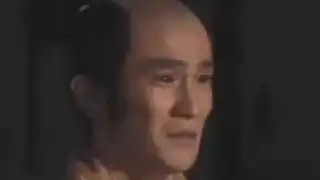偉人
偉人高木盛之輔
たかぎ もりのすけ(1854-1919)
登場回数:1作
高木 盛之輔(たかぎ もりのすけ/たかき もりのすけ、1854年(安政1年) - 1919年(大正8年)2月19日)は、日本の武士、検察官。会津藩藩士として戊辰戦争を、別働第二旅団の一員として西南戦争を戦った。姉の高木時尾は照姫附き祐筆で、元新撰組副長助勤斎藤一(藤田五郎)に嫁ぐ。福島県立会津高等学校の創立功労者の一人である。
登場回数:1作
高木 盛之輔(たかぎ もりのすけ/たかき もりのすけ、1854年(安政1年) - 1919年(大正8年)2月19日)は、日本の武士、検察官。会津藩藩士として戊辰戦争を、別働第二旅団の一員として西南戦争を戦った。姉の高木時尾は照姫附き祐筆で、元新撰組副長助勤斎藤一(藤田五郎)に嫁ぐ。福島県立会津高等学校の創立功労者の一人である。