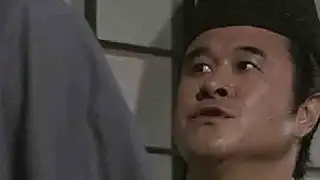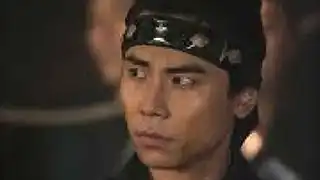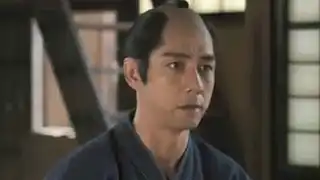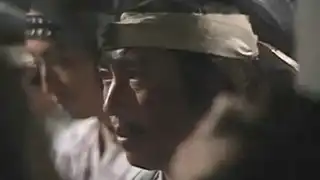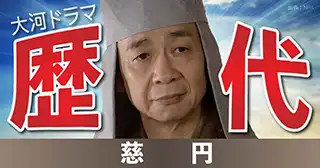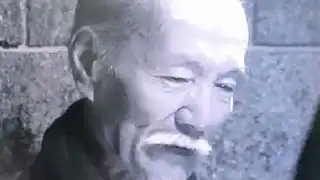 偉人
偉人三浦梧楼
みうら ごろう(1847-1926)
登場回数:1作
三浦 梧楼(みうら ごろう、旧字体:三浦 梧樓、弘化3年11月15日〈1847年1月1日〉 - 大正15年〈1926年〉1月28日)は、日本の陸軍軍人、政治家。 最終階級は陸軍中将。栄典は従一位勲一等子爵。号は観樹。
登場回数:1作
三浦 梧楼(みうら ごろう、旧字体:三浦 梧樓、弘化3年11月15日〈1847年1月1日〉 - 大正15年〈1926年〉1月28日)は、日本の陸軍軍人、政治家。 最終階級は陸軍中将。栄典は従一位勲一等子爵。号は観樹。