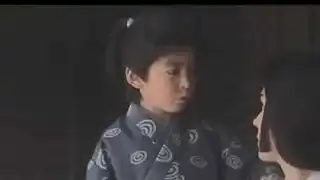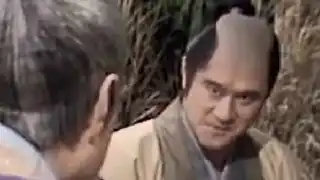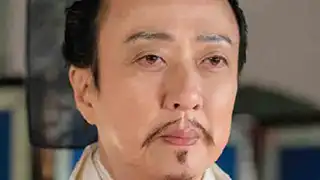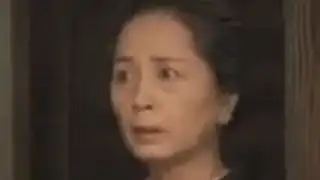 偉人
偉人新島とみ
にじいま とみ(1807-1896)
登場回数:1作
新島 とみ(にじいま とみ 1807年10月10日〈文化4年9月9日〉 - 1896年〈明治29年〉1月7日)は、武蔵国浦和宿(現:埼玉県さいたま市浦和区)出身の人物。同志社大学創設者、新島襄の母。旧姓田中とみ。新島登美と表記される場合もある。
登場回数:1作
新島 とみ(にじいま とみ 1807年10月10日〈文化4年9月9日〉 - 1896年〈明治29年〉1月7日)は、武蔵国浦和宿(現:埼玉県さいたま市浦和区)出身の人物。同志社大学創設者、新島襄の母。旧姓田中とみ。新島登美と表記される場合もある。