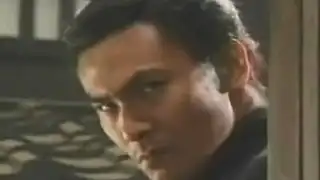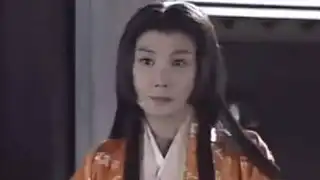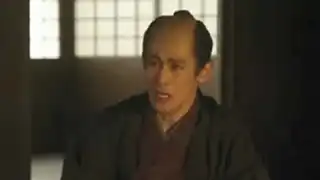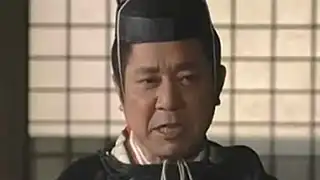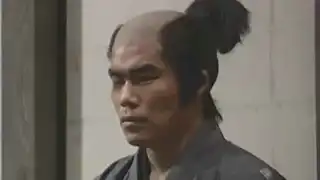偉人
偉人下間頼廉
しもつま らいれん(1537-1626)
登場回数:1作
下間 頼廉(しもつま らいれん、天文6年(1537年)- 寛永3年6月20日(1626年8月11日))は、戦国時代から江戸時代の僧侶、武将。石山本願寺の坊官。下間頼康の子。母は下間頼次の娘。子に頼亮、宗清、仲玄、下間仲世室、牧長勝室、端坊明勝室、川那部宗甫室。幼名は虎寿、通称は源十郎、右衛門尉。剃髪し刑部卿と号す。法名は了入、了悟。法橋、法眼、法印に任ぜられる。
登場回数:1作
下間 頼廉(しもつま らいれん、天文6年(1537年)- 寛永3年6月20日(1626年8月11日))は、戦国時代から江戸時代の僧侶、武将。石山本願寺の坊官。下間頼康の子。母は下間頼次の娘。子に頼亮、宗清、仲玄、下間仲世室、牧長勝室、端坊明勝室、川那部宗甫室。幼名は虎寿、通称は源十郎、右衛門尉。剃髪し刑部卿と号す。法名は了入、了悟。法橋、法眼、法印に任ぜられる。