山本勘助
やまもと かんすけ(1493-1561)
登場回数:2作
別名:山本源助/大林源助/大林勘助
山本 菅助(やまもと かんすけ)は、戦国時代の武将。 『甲陽軍鑑』においては名を勘助、諱を晴幸、出家後道鬼を称したという。勘助の諱・出家号については文書上からは確認されていなかったが、近年、沼津山本家文書「御証文之覚」「道鬼ヨリ某迄四代相続仕候覚」により、江戸時代段階で山本菅助子孫が諱を「晴幸」、出家号を「道鬼」と認識していたことは確認された。ただし「晴幸」の諱については、明治25年(1892年)に星野恒が「武田晴信(信玄)が家臣に対し室町将軍足利義晴の偏諱である「晴」字を与えることは社会通念上ありえなかった」とも指摘している。 『甲陽軍鑑』巻九では天文16年に武田晴信が『甲州法度之次第』を定めた際に菅助の年齢を55歳としており、これに従うと生年は明応2年(1493年)となる。一方、『甲陽軍鑑』末書下巻下の「山本勘介うハさ。五ヶ条之事」によれば、勘助の生年を明応9年(1500年)としている。「五ヶ条之事」では菅助が本国を出て武者修行を行い、駿河で滞在し今川家に仕官を望み、甲斐へ移り武田家に仕官し、出家し川中島の戦いで戦死する一連の履歴の年齢を記しているが、これには矛盾が存在していることが指摘される。生年には、文亀元年(1501年)説もある。『甲陽軍鑑』によれば、没年は永禄4年(1561年)9月10日の川中島の戦いで討死したとされる。 近世には武田二十四将に含められ、武田の五名臣の一人にも数えられて、武田信玄の伝説的軍師としての人物像が講談などで一般的となっているが、「山本勘助」という人物は『甲陽軍鑑』やその影響下を受けた近世の編纂物以外の確実性の高い史料では一切存在が確認されていないために、その実在について長年疑問視されていた。しかし近年は「山本勘助」と比定できると指摘される「山本菅助」の存在が複数の史料で確認されている。
 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人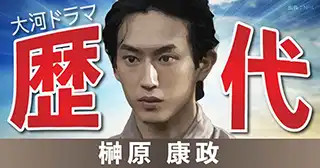 偉人
偉人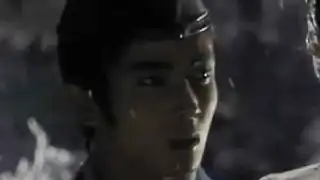 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人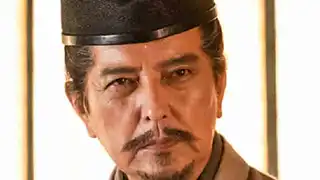 偉人
偉人 偉人
偉人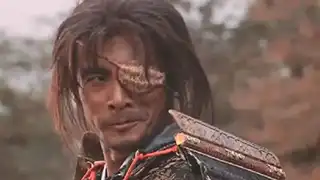 偉人
偉人 偉人
偉人