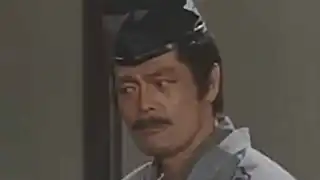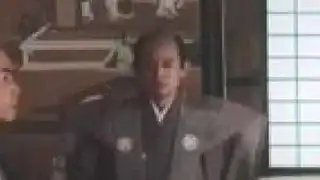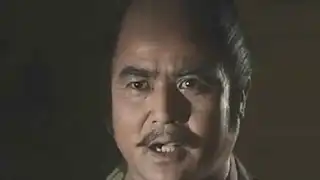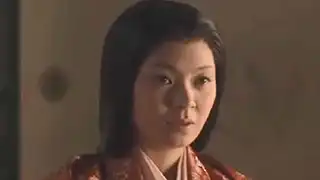偉人
偉人山本久栄
やまもと ひさえ(1871-1893)
登場回数:1作
山本 久栄(やまもと ひさえ、1871年(明治4年) - 1893年(明治26年)7月20日)は、明治時代の社会事業家である。徳富蘆花の小説『黒い眼と茶色の目』のヒロイン寿代(ひさよ)のモデルとなった人物で、蘆花の初恋の相手でもある。小説の題名のうち、黒い眼は新島襄を、茶色の目は山本久栄を指す。
登場回数:1作
山本 久栄(やまもと ひさえ、1871年(明治4年) - 1893年(明治26年)7月20日)は、明治時代の社会事業家である。徳富蘆花の小説『黒い眼と茶色の目』のヒロイン寿代(ひさよ)のモデルとなった人物で、蘆花の初恋の相手でもある。小説の題名のうち、黒い眼は新島襄を、茶色の目は山本久栄を指す。