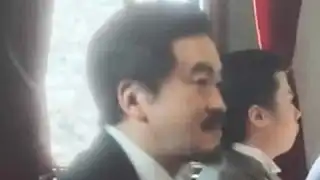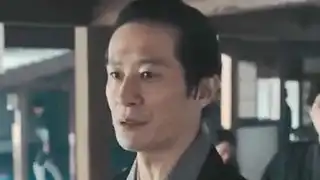 偉人
偉人前島密
まえじま ひそか(1835-1919)
登場回数:1作
前島 密(まえじま ひそか、天保6年1月7日〈1835年2月4日〉 - 大正8年〈1919年〉4月27日)は、日本の官僚、政治家、華族。位階勲等爵位は従二位勲二等男爵。本姓は上野。幼名は房吾郎。名(諱)は巻退蔵、密。通称は来輔。号は如々山翁鴻爪。 越後国出身。日本の近代郵便制度の主要な創設者の一人であり「日本近代郵便の父」と呼ばれる。今日も使われる「郵便」「切手」「葉書」という名称を定めたほか、1円切手の肖像で知られる。また、東京専門学校及び早稲田大学の建学に深く関わり、早稲田大学校賓の名誉を受けている。
登場回数:1作
前島 密(まえじま ひそか、天保6年1月7日〈1835年2月4日〉 - 大正8年〈1919年〉4月27日)は、日本の官僚、政治家、華族。位階勲等爵位は従二位勲二等男爵。本姓は上野。幼名は房吾郎。名(諱)は巻退蔵、密。通称は来輔。号は如々山翁鴻爪。 越後国出身。日本の近代郵便制度の主要な創設者の一人であり「日本近代郵便の父」と呼ばれる。今日も使われる「郵便」「切手」「葉書」という名称を定めたほか、1円切手の肖像で知られる。また、東京専門学校及び早稲田大学の建学に深く関わり、早稲田大学校賓の名誉を受けている。