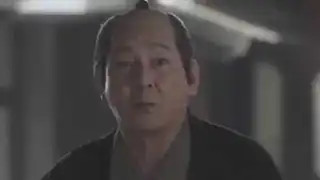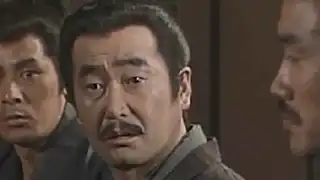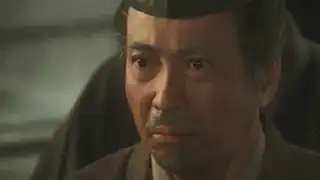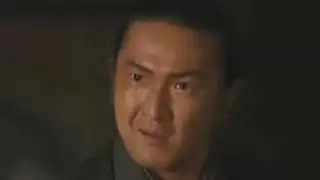偉人
偉人荒木田守武
あらきだ もりたけ(1473-1549)
登場回数:1作
荒木田 守武(あらきだ もりたけ、文明5年(1473年) - 天文18年8月8日(1549年8月30日))は、戦国時代の伊勢神宮祠官・連歌師。荒木田一門薗田氏の出身で、父は荒木田守秀、母は荒木田(藤波)氏経の娘。荒木田守晨の弟。山崎宗鑑とともに俳諧の祖とも言われている。通称は中川平太夫と言った。77歳で病没。 1541年(天文10年)一禰宜となると当時流行していた連歌を三条西実隆に師事し、宗祇・宗長と交流があった。「新撰菟玖波集」に入集1句をはじめ、「法楽発句集」(1508年/永正5年)などの連歌集、「独吟百韻」(1530年/享禄3年)、「守武千句」(1540年/天文9年)などの俳諧集、教訓歌集「世中百首」(1525年/大永5年)などを残した。
登場回数:1作
荒木田 守武(あらきだ もりたけ、文明5年(1473年) - 天文18年8月8日(1549年8月30日))は、戦国時代の伊勢神宮祠官・連歌師。荒木田一門薗田氏の出身で、父は荒木田守秀、母は荒木田(藤波)氏経の娘。荒木田守晨の弟。山崎宗鑑とともに俳諧の祖とも言われている。通称は中川平太夫と言った。77歳で病没。 1541年(天文10年)一禰宜となると当時流行していた連歌を三条西実隆に師事し、宗祇・宗長と交流があった。「新撰菟玖波集」に入集1句をはじめ、「法楽発句集」(1508年/永正5年)などの連歌集、「独吟百韻」(1530年/享禄3年)、「守武千句」(1540年/天文9年)などの俳諧集、教訓歌集「世中百首」(1525年/大永5年)などを残した。