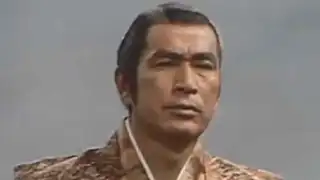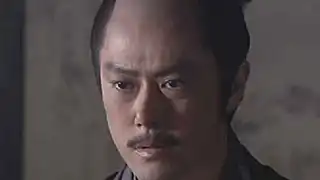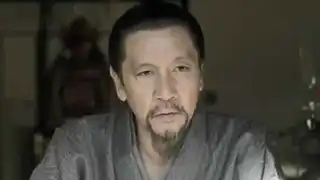偉人
偉人孝蔵主
こうぞうす(?-1626)
登場回数:7作
孝蔵主(こうぞうす、? - 寛永3年4月14日(1626年5月9日))は、安土桃山時代から江戸時代初期に活躍した女性。豊臣秀吉の正室・高台院付きの筆頭上臈で、後に徳川秀忠付き上臈となった。「孝蔵主」は上臈としての雅名であり、実名は不明。
登場回数:7作
孝蔵主(こうぞうす、? - 寛永3年4月14日(1626年5月9日))は、安土桃山時代から江戸時代初期に活躍した女性。豊臣秀吉の正室・高台院付きの筆頭上臈で、後に徳川秀忠付き上臈となった。「孝蔵主」は上臈としての雅名であり、実名は不明。