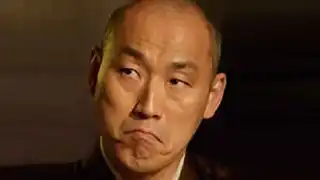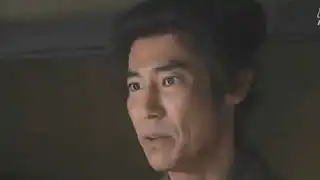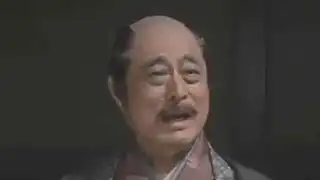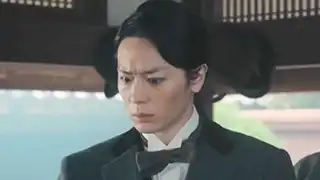偉人
偉人巴御前
ともえごぜん(?-?)
登場回数:3作
巴御前(ともえごぜん、生没年不詳)は、平安時代末期の信濃国の女性。女武者として伝えられている。字は鞆、鞆絵とも。『平家物語』によれば源義仲に仕える女武者。『源平闘諍録』によれば樋口兼光の娘。『源平盛衰記』によれば中原兼遠の娘、樋口兼光・今井兼平の姉妹で、源義仲の妾。
登場回数:3作
巴御前(ともえごぜん、生没年不詳)は、平安時代末期の信濃国の女性。女武者として伝えられている。字は鞆、鞆絵とも。『平家物語』によれば源義仲に仕える女武者。『源平闘諍録』によれば樋口兼光の娘。『源平盛衰記』によれば中原兼遠の娘、樋口兼光・今井兼平の姉妹で、源義仲の妾。