 偉人
偉人鎌田光政
かまだ みつまさ(?-1185)
登場回数:2作
鎌田 光政(かまだ みつまさ)は、平安時代末期の武将。名は政光、正親とも。源義朝の乳兄弟である鎌田政清の子(鎌田政治の子という説も)。兄は鎌田 盛政(かまた もりまさ)で通称は藤太。
登場回数:2作
鎌田 光政(かまだ みつまさ)は、平安時代末期の武将。名は政光、正親とも。源義朝の乳兄弟である鎌田政清の子(鎌田政治の子という説も)。兄は鎌田 盛政(かまた もりまさ)で通称は藤太。
 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人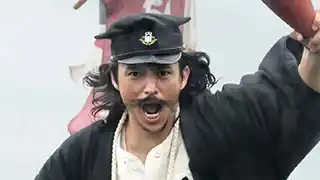 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人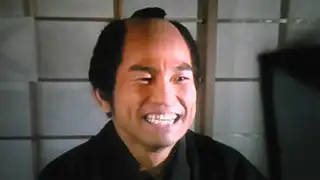 偉人
偉人 偉人
偉人