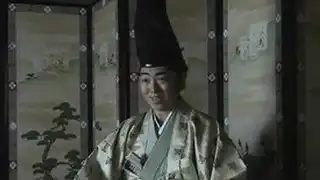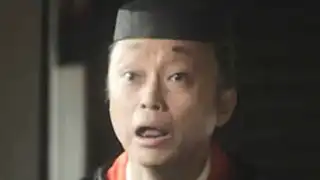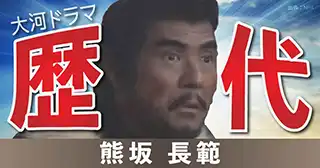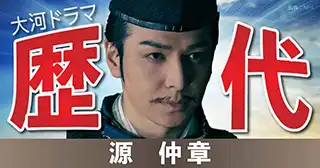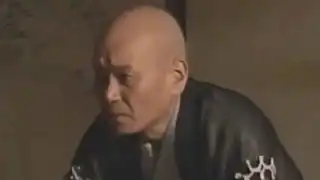 偉人
偉人曲直瀬道三
まなせ どうさん(1507-1594)
登場回数:3作
曲直瀬 道三(まなせ どうさん、永正4年9月18日(1507年10月23日) - 文禄3年1月4日(1594年2月23日))は、戦国時代から安土桃山時代の日本の医師。道三は号。諱は正盛(しょうせい/まさもり)または正慶(まさよし)。字は一渓。他に雖知苦斎(すいちくさい)、翠竹庵(すいちくあん)、啓迪庵(けいてきあん)など。本姓は元は源朝臣(宇多源氏)、のち橘朝臣。今大路家の祖。日本医学中興の祖として田代三喜・永田徳本などと並んで「医聖」と称される。養子に曲直瀬玄朔があり、後に2代目「道三」を襲名している。
登場回数:3作
曲直瀬 道三(まなせ どうさん、永正4年9月18日(1507年10月23日) - 文禄3年1月4日(1594年2月23日))は、戦国時代から安土桃山時代の日本の医師。道三は号。諱は正盛(しょうせい/まさもり)または正慶(まさよし)。字は一渓。他に雖知苦斎(すいちくさい)、翠竹庵(すいちくあん)、啓迪庵(けいてきあん)など。本姓は元は源朝臣(宇多源氏)、のち橘朝臣。今大路家の祖。日本医学中興の祖として田代三喜・永田徳本などと並んで「医聖」と称される。養子に曲直瀬玄朔があり、後に2代目「道三」を襲名している。