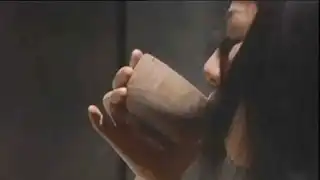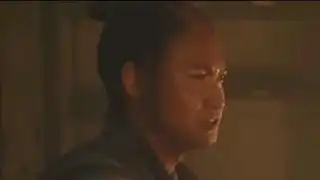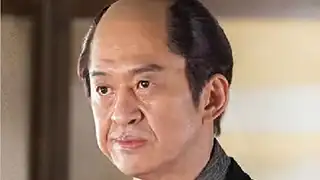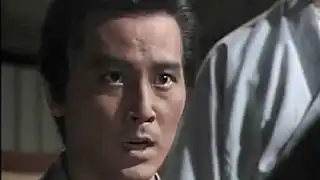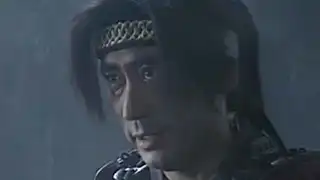偉人
偉人古橋廣之進
ふるはし ひろのしん(1928-2009)
登場回数:1作
古橋 廣之進(ふるはし ひろのしん、1928年(昭和3年)9月16日 - 2009年(平成21年)8月2日)は、日本の水泳選手でありスポーツ指導者。日本大学名誉教授。フジヤマのトビウオの異名を持つ。 第二次世界大戦終了後の水泳界で次々と世界記録を打ち立てた。現役引退後は大同毛織(現 ダイドーリミテッド)に入社。その後、母校・日本大学の教授や日本水泳連盟会長、日本オリンピック委員会会長を歴任した。2009年(平成21年)8月2日、世界水泳選手権が開かれていたイタリア・ローマで死去した。
登場回数:1作
古橋 廣之進(ふるはし ひろのしん、1928年(昭和3年)9月16日 - 2009年(平成21年)8月2日)は、日本の水泳選手でありスポーツ指導者。日本大学名誉教授。フジヤマのトビウオの異名を持つ。 第二次世界大戦終了後の水泳界で次々と世界記録を打ち立てた。現役引退後は大同毛織(現 ダイドーリミテッド)に入社。その後、母校・日本大学の教授や日本水泳連盟会長、日本オリンピック委員会会長を歴任した。2009年(平成21年)8月2日、世界水泳選手権が開かれていたイタリア・ローマで死去した。