 偉人
偉人山吉盛侍
やまよし もりひと)は(1671-1753)
登場回数:4作
別名:山吉新八郎
山吉 盛侍(やまよし もりひと)は、江戸時代前期から中期にかけての武士。吉良義央の家臣 ・近習(吉良義周の中小姓)。通称は新八郎(しんぱちろう)。
登場回数:4作
別名:山吉新八郎
山吉 盛侍(やまよし もりひと)は、江戸時代前期から中期にかけての武士。吉良義央の家臣 ・近習(吉良義周の中小姓)。通称は新八郎(しんぱちろう)。
 偉人
偉人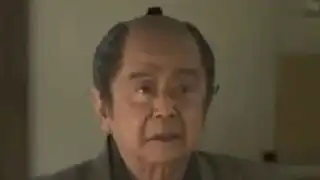 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人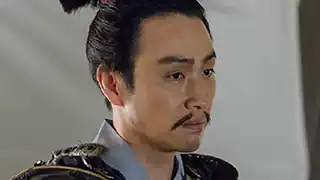 偉人
偉人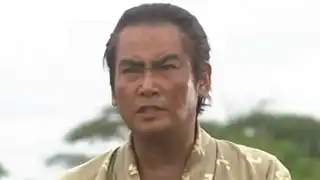 偉人
偉人 偉人
偉人