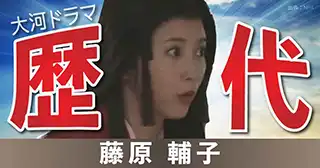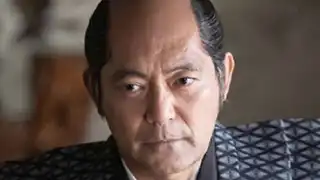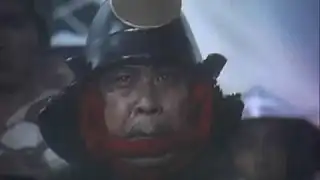偉人
偉人藤原宗輔
ふじわら の むねすけ(1077-1162)
登場回数:1作
藤原 宗輔(ふじわら の むねすけ)は、平安時代後期の公卿。藤原北家中御門家(松木家)の祖、権大納言・藤原宗俊の子。官位は従一位・太政大臣。堀河または京極と号する。「蜂飼大臣(はちかいおとど)」の異名で『今鏡』『十訓抄』にも登場する。
登場回数:1作
藤原 宗輔(ふじわら の むねすけ)は、平安時代後期の公卿。藤原北家中御門家(松木家)の祖、権大納言・藤原宗俊の子。官位は従一位・太政大臣。堀河または京極と号する。「蜂飼大臣(はちかいおとど)」の異名で『今鏡』『十訓抄』にも登場する。