 偉人
偉人副島道正
そえじま みちまさ(1871-1948)
登場回数:1作
副島 道正(そえじま みちまさ、1871年11月26日〈明治4年10月14日〉 - 1948年〈昭和23年〉10月13日)は、明治から昭和期の華族、実業家、IOC委員。伯爵。
登場回数:1作
副島 道正(そえじま みちまさ、1871年11月26日〈明治4年10月14日〉 - 1948年〈昭和23年〉10月13日)は、明治から昭和期の華族、実業家、IOC委員。伯爵。
 偉人
偉人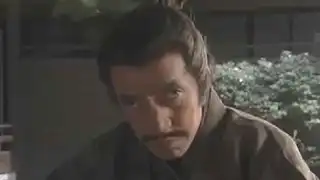 偉人
偉人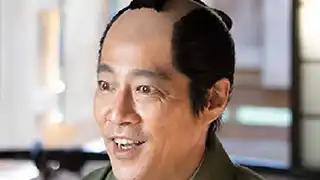 偉人
偉人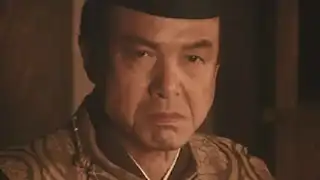 偉人
偉人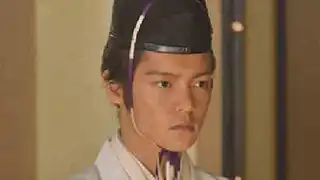 偉人
偉人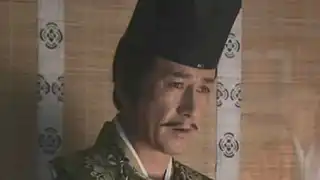 偉人
偉人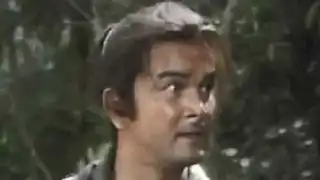 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人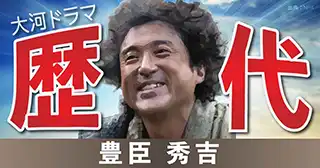 偉人
偉人