生島新五郎
いくしま しんごろう(1671-1743)
登場回数:1作
生島 新五郎(いくしま しんごろう、寛文11年(1671年) - 寛保3年1月5日(1743年1月30日))は、江戸時代中期の歌舞伎役者。江戸城大奥の月光院付きの御年寄であった江島と共に、江島生島事件の中心人物である。一方で、生島半六(初代 市川團十郎を刺殺した犯人)や二代目 市川團十郎の師匠の一人でもある。 大坂生まれ。貞享元年(1684年)に野田蔵之丞の名で木挽町の芝居小屋・山村座の舞台に立つ。元禄4年(1691年)、生島新五郎と改名。当時を代表する人気役者となった。 正徳4年(1714年)、大奥御年寄の江島が寺へ参詣した帰途、新五郎の舞台を観覧し、その後宴会を開いたことで大奥の門限に遅れ、大きな問題となった。このことから江島との密会が疑われ、捕縛の上、石抱の拷問にかけられ、「自白」させられた。評定所が審理した結果、新五郎に三宅島へ遠島(流罪)の裁決が下る。また、山村座の座元も伊豆大島への遠島となって、山村座は廃座となった。 寛保2年(1742年)2月、徳川吉宗により赦免され江戸に戻ったが、翌年小網町にて73歳で没する。ただし、享保18年(1733年)に三宅島で死去したという説もある。戒名は道栄信士。墓所は三宅島にある。 この事件を題材にした川柳に「やつさずに濡れ事をする新五郎」がある。「やつす」とは「化粧をする」という意味。
 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人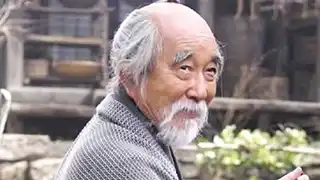 偉人
偉人 偉人
偉人 偉人
偉人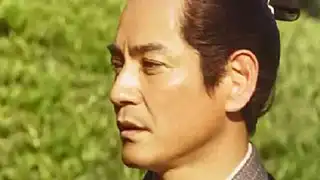 偉人
偉人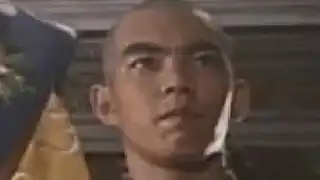 偉人
偉人