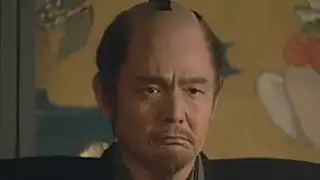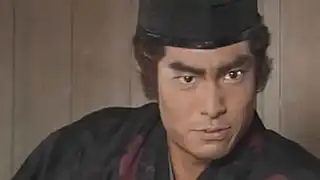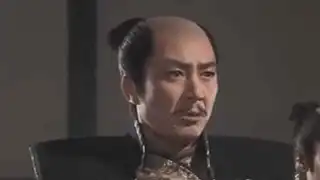 偉人
偉人藤堂高虎
とうどう たかとら(1556-1630)
登場回数:8作
藤堂 高虎(とうどう たかとら)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・大名。伊予今治藩主、後に伊勢津藩の初代藩主となる。津藩藤堂家(藤堂家宗家)初代。 藤堂高虎は、黒田孝高、加藤清正と並び、「築城三名人」の一人と称される。数多くの築城の縄張りを担当し、層塔式天守を考案。高石垣の技術をはじめ、石垣上には多聞櫓を巡らす築城の巧みさは、その第一人者といっても過言ではない。また外様大名でありながら徳川家康の側近として幕閣にも匹敵する実力を持つ、異能の武将であったといえる。
登場回数:8作
藤堂 高虎(とうどう たかとら)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・大名。伊予今治藩主、後に伊勢津藩の初代藩主となる。津藩藤堂家(藤堂家宗家)初代。 藤堂高虎は、黒田孝高、加藤清正と並び、「築城三名人」の一人と称される。数多くの築城の縄張りを担当し、層塔式天守を考案。高石垣の技術をはじめ、石垣上には多聞櫓を巡らす築城の巧みさは、その第一人者といっても過言ではない。また外様大名でありながら徳川家康の側近として幕閣にも匹敵する実力を持つ、異能の武将であったといえる。