亀山天皇
かめやまてんのう(1249-1305)
登場回数:1作
別名:恒仁/亀山上皇
亀山天皇(かめやまてんのう、1249年7月9日〈建長元年5月27日〉- 1305年10月4日〈嘉元3年9月15日〉)は、日本の第90代天皇(在位:1260年1月9日〈正元元年11月26日〉- 1274年3月6日〈文永11年1月26日〉)。諱は恒仁(つねひと)。 後嵯峨天皇の皇子。母は中宮・西園寺姞子(大宮院)。后腹では後深草天皇に次ぐ次男。南朝(大覚寺統)の祖。父母から鍾愛され、兄の後深草天皇を差し置いて治天の君となり、やがて亀山系の南朝と後深草系の北朝(持明院統)による対立が生じる端緒となった。 皇家の人間ながら、当時の新興宗教である禅宗・律宗を手厚く保護した。五山別格とされ臨済宗寺格第一である南禅寺は、無関普門(大明国師)に帰依した亀山天皇の勅願によるものである。また、真言律宗の開祖である西大寺の叡尊(興正菩薩)にも深く帰依した。禅律振興政策は孫である後醍醐天皇、および後醍醐を敬愛した足利尊氏に継承された。 元寇(文永の役(1274年)、弘安の役(1281年))時の治天の君でもある(天皇は子の後宇多天皇)。
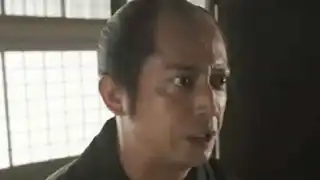 偉人
偉人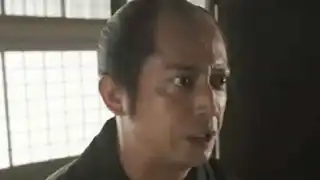 偉人
偉人 偉人
偉人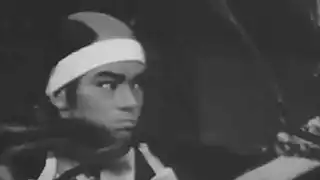 偉人
偉人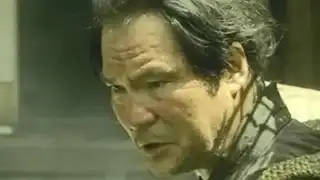 偉人
偉人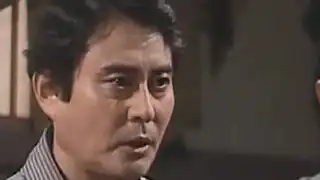 偉人
偉人 偉人
偉人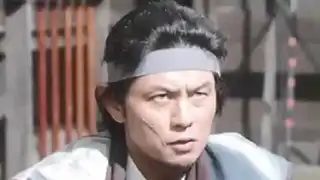 偉人
偉人 偉人
偉人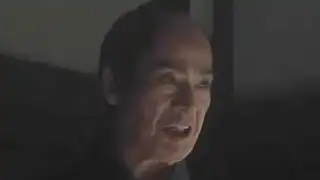 偉人
偉人 偉人
偉人