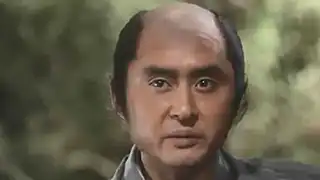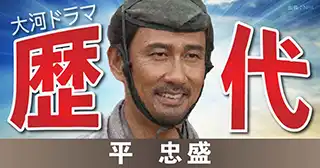偉人
偉人武田信賢
たけだ のぶかた(1420-1471)
登場回数:1作
武田 信賢(たけだ のぶかた)は、室町時代中期から後期にかけての武将・守護大名。若狭・丹後守護、安芸佐東郡・安南郡・山県郡守護。安芸武田氏5代・若狭武田氏2代当主。安芸武田氏の武田信繁の次男。兄に信栄、弟に国信、元綱。家系には異説がある。
登場回数:1作
武田 信賢(たけだ のぶかた)は、室町時代中期から後期にかけての武将・守護大名。若狭・丹後守護、安芸佐東郡・安南郡・山県郡守護。安芸武田氏5代・若狭武田氏2代当主。安芸武田氏の武田信繁の次男。兄に信栄、弟に国信、元綱。家系には異説がある。