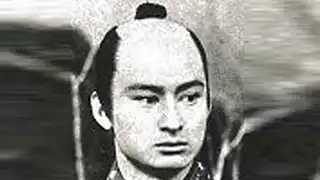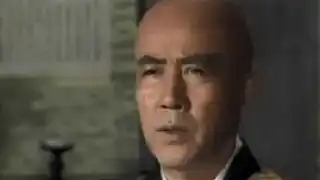偉人
偉人加納久通
かのう ひさみち(1673-1748)
登場回数:1作
加納 久通(かのう ひさみち)は、江戸時代中期の大名。初代八田藩主。江戸幕府8代将軍徳川吉宗の紀州時代からの側近。通称は孫市、角兵衛。官途名は近江守、遠江守。一宮藩加納家初代。紀州藩士から幕臣となり、御側御用取次から西ノ丸若年寄まで出世した。
登場回数:1作
加納 久通(かのう ひさみち)は、江戸時代中期の大名。初代八田藩主。江戸幕府8代将軍徳川吉宗の紀州時代からの側近。通称は孫市、角兵衛。官途名は近江守、遠江守。一宮藩加納家初代。紀州藩士から幕臣となり、御側御用取次から西ノ丸若年寄まで出世した。